Project story 02 “見える化”が現場を変える

vol.2
CloudOwl×I-INFLAP誕生ものがたり
機械メーカーの常識を覆すイシダのシステム開発とは!?
Project Team プロジェクトメンバー

開発リーダー S・F(2017年入社)
第二開発部 システム開発一課
豊富な知識と熱いリーダーシップで開発の軸となる存在。

開発担当 T・E(2022年入社)
第二開発部 システム開発一課
入社1年目で本プロジェクトに抜擢された期待の新人。丁寧な対話と柔軟な発想で連携仕様を設計。

営業担当(西日本)Y・K(2012年入社)
DX・SIベンダー部 営業三課
現場での違和感を見逃さない観察眼と突破力で、本プロジェクトを動かした発起人。

営業担当(東日本)H・H(2018年入社)
DX・SIベンダー部 営業三課
システム導入フェーズで全国の工場を飛び回り、現場の不安を解消。
Project Outline プロジェクトアウトライン
1.気づきから始まった提案型プロジェクト。
イシダは長年、食品製造の進化を支える計量・包装・検査機器と、それらを連携させる先進的なシステム開発に注力してきた。そこで一貫して大切にしているのは、「製品やサービスだけではなく、現場の課題に応えるソリューションを届けたい」という姿勢。製品の開発から導入支援まで、常にその視点が私たちのDNAとして息づいている。今回のプロジェクトのきっかけも、お客様の要望ではなく、現場を訪れた営業担当の小さな気づきからだった。深夜でも責任者が現場対応に追われている様子を前に、「これは何とかできないか」と開発部に相談を持ちかけた。動き出したプロジェクトはシステム開発に成功し、お客様のビジネスに新たな価値をもたらした。
2.イシダの2製品の連携で、現場の仕組みを変える。
プロジェクトチームが目指したのは、イシダのIoTシステム「Cloud Owl」と画像検査装置「i-INFLAP」の連携によって、食品検査の結果履歴やNGの傾向をリアルタイムで把握できる仕組みを構築すること。不良の発生をすばやく察知し、遠隔からの判断と対応を可能にする現場支援の基盤だ。現場責任者が工場に駆けつけることなく、タブレットやPCで状況を確認し意思決定ができるようになり、「働き方が変わった」といった感謝の声も寄せられている。この取り組みは、システムがどう使われるか、どんな価値を生み出すかまで考え抜いた提案であり、運用そのものを劇的に改善する仕組みづくりだった。お客様の現場に深く入ることで要望を捉え、使われる形を設計する。その視点こそが、イシダが目指す “コト売り”(継続的な課題解決)の姿だった。
Chapter 1 第1章

本当に必要なものは、真のソリューションだった。
イシダの開発の原点は、現場の課題に気づき、お客様に解決策を提案することにある。今回のプロジェクトも、営業の現場での気づきから始まった。営業のKが訪れたのは、コンビニ向けの弁当・総菜を製造する食品工場。そこではすでに、ラベルの印字内容や貼り付け状態を検査するイシダの「i-INFLAP」が稼働していた。しかし、不具合が起きれば、工場の責任者が夜間や休日であっても現場に駆けつける必要があり、検査機器はあるが、緊急対応は人が行っている状態であった。その運用を見て、Kは「必要なのは検査装置を活かす仕組みだ」と考えた。そして、開発部に相談を持ちかけた。

相談を受けたのは、開発リーダーのFと、ソフト設計を担うEだった。2人が描いた構想は、遠隔で生産ラインの稼働状況を把握できるイシダのIoTシステム「Cloud Owl」と、「i-INFLAP」を連携させること。検査でNGが発生した時に即時に状況を把握し、対応できる体制をつくるというものだった。
Chapter 2 第2章
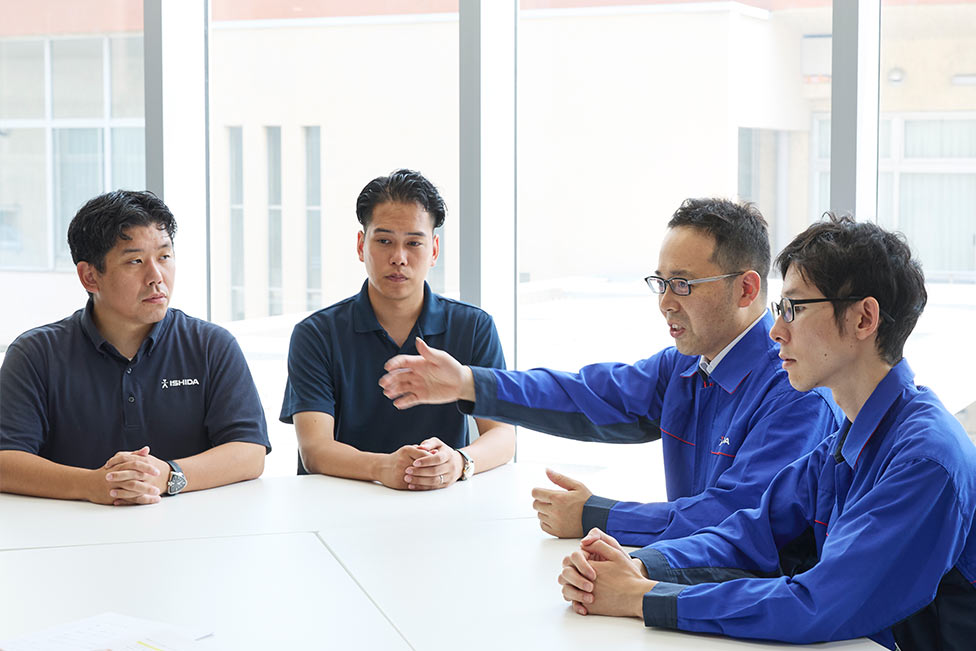
「役に立つ仕組みをつくる」、という挑戦。
今回のプロジェクトで最も重要なテーマは、自社製品の連携ではない。現場で「本当に役に立つ仕組み」をつくり上げることだった。そのためにお客様の工場へ足を運び、管理者や作業員の方が何を見てどう判断しているのか、現場を徹底的に観察・ヒアリングし、一つひとつ設計に落とし込んでいった。

開発と営業は、現場を常にイメージし、意見を持ち寄った。設計思想をぶつけ合い、テスト環境で実際に動かしながら仕様を詰めていった。この密なコミュニケーションの積み重ねが、本当に「役に立つ仕組み」の土台となっていった。
さらに開発チームは、工場内設備のさまざまな連携を模索しながら、システム負荷の軽減についても検討を重ねた。カメラ画像と検査結果のずれ、データフォーマットの調整などの地道な検証と修正を経て課題を乗り越え、信頼性が高く真に役立つソリューションができあがっていった。
Chapter 3 第3章

「現場に本当にフィットする仕組み」を追求。
「Cloud Owl」と「i-INFLAP」の連携が形になり、全国12工場への導入が本格的に始まった。工場ごとに生産品目や設備、運用ルールが異なる中で、どこでも使える統一性と、現場事情に応じた柔軟性の両方が求められた。ここで営業としてプロジェクトに加わったのがH。各工場の課題を拾い上げ、導入計画や支援体制を整えていった。

また、本プロジェクトでは開発が現場支援に深く関わり、装置のセットアップやテスト稼働までを直接サポートする体制がとられた。開発担当は工場に入り、現場との対話を通じて調整作業を進めていった。その過程で、実際の運用を把握しながら製品仕様を微調整し、「現場に本当にフィットする仕組み」へと近づけていった。営業と開発が連携し、現場に深く関わったことで、導入先からの信頼も厚くなった。現場からは、「不良品を生産しないよう、以前は夜中でもNGが出れば対応が必要だったが、遠隔地からタブレットで確認できるようになった」「働き方にゆとりができた」といった喜びの声も届いた。365日、24時間、安全で安心な食を享受できているのは、食品工場や食品製造機械、そしてそのシステムが影でしっかりと稼働し続けているからだ。
Chapter 4 第4章

定着から進化へ──“見える化”のその先へ
当初の目的は、現場管理の質の向上と、作業の手間を減らす省力化だった。導入後は、NGの履歴や作業状況が可視化されたことで、「この数値も見たい」「このような条件で分析したい」といった新たな要望が自然に上がるようになった。この仕組みが、工場内の働きやすさ追求、意識向上のきっかけにもなり始めているのだ。
イシダは今後、こうした声をもとに、他製品や他社装置との連携にも対応できるよう、仕組みの拡張を構想している。現場に根ざした改善の積み重ねが、次の提案や製品を育てていく。製品・システムの提供にとどまらず、その先の成果や運用にまで踏み込む“コトづくり” (真の成果追及)の姿勢が、今回の取り組みを通じて改めて明確になった。
Summary 最後に
真の課題に気づき、真のソリューションをつくる。その力がイシダにはある。今回のプロジェクトの根底には、「お客様の真の課題に気づき、部門を超えて連携し解決する」というイシダの文化が根付いている。社内のさまざまな関係者が、「現場に本当に役立つものづくり」を目指して動いた。また、現場に目を向け、重要な課題には、仲間を信じてアクションを起こす。その一歩から始まった取り組みが、全国12工場への展開へとつながったのは、共通の目標に向かって、知恵を出し合い、手を動かし、相手を思いながら、より良いものを作ろうとする姿勢があったからだ。こうした積み重ねが、製品を強くし、会社を成長へと導く。いまや機械メーカーという枠にとらわれることなく、多様な食品製造機器を繋ぐシステムまで開発しているイシダ。現場の声に耳を傾け、部門を超えて連携する姿勢が根付いているからこそ、お客様の課題を革新的に解決し続けることができている。
Project Message プロジェクトメッセージ
イシダでは、部門の枠を超えて、ひとつの課題にチームで取り組む文化が根づいています。今回のプロジェクトも、営業の気づきからスタートし、開発との綿密な連携によって「検査装置」から「現場全体を支える仕組み」へと進化させることができました。イシダが届けたいのは、目の前の機械だけでなく、それを通して得られる安心や効率、そしてより良い現場の未来です。あなたも、イシダで“まだこの世にない価値”をつくる挑戦をしてみませんか?あなたの視点が、きっと次の現場を変える力になります。
Technology & Products イシダの技術と製品
Recruit Contact お問い合わせ
採用についてのお問い合わせは
お気軽にどうぞ。
Recruitment 採用情報
あなたのエントリーをお待ちしています。
- 新卒採用TOP
- イシダの技術と製品
- プロジェクトストーリー
- プロジェクトストーリー02
