秤を制御する
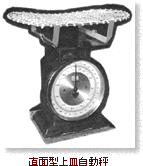

昭和28年はあらゆる意味で我が国経済にとって重要なターニングポイントでした。国家財政安定のための緊縮政策を公共投資、財政等融資の増強をし積極財政を打ち出しました。
石田衡器製作所がこの年に開発、発売した三つの製品はいずれも「当時の秤を制御する技術」では画期的なものでした。
1).下皿バネ式指示秤
最小目盛600分の1の、載皿を下方に置く新機構を採用。中央計量検定所では400分の1の最小目盛が認定の限度となっていたのでしたが、当社は独自の技術で精度の限界に挑戦。制温装置付自動指示秤でわが国初の600分の1表示で認定された画期的製品でした。引続いて800分の1の精度の認定を受けていました。この下皿秤は秤が電子化されるまで、その精度の高さと使い易さから戦後の高精度商業秤としての役割を果たします。
2).「石田式自動上皿天秤」
従来の調剤用天秤が構造上の不備もあり使用上にもいろいろ問題があった点を改良したものでした。精度、操作性など従来製品をはるかに上回り、とくに5グラムまでは目盛板に表示されるため小分銅を必要としない点が最大の特長でした。
3).「定量秤」
一定量の被計量物を連続的に正しく計量するという新しいタイプの秤でした。技術的には計量の際、指針をすばやく停止させる振止装置(オイルダンパー)の開発が高く評価され、以後の定量秤の改良、開発に大きな役割を演じることになりました。オイルダンパー自身は以前からありましたが、シリンダーとピストンを無接触とした新しい試みの物でした。
なお、秤を制御するという考え方は、戦前の不変敏感自動秤、あるいは昭和24年のバイメタル式制温装置付自動ばね秤などに見られるとおり、石田衡器製作所の一貫した製品開発姿勢、商品哲学を示すもので、この考え方が後年のコンピュータスケール、あるいは産業用計算システムなどに展開していきます。
