江戸と京都に
秤座あり
西暦593~1867
奈良時代~江戸時代中期
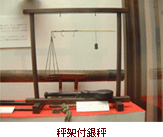
モノの重さの単位としてもっぱら「斤」が使われていた古代を過ぎ、奈良時代に入ると斗・升・斤・両が定められます。 また土地の大きさから、税として納める布の大きさ、果ては君臣のお墓の大きさまでが尺度を使って定められます。
法としてきちんと規定されたのは701年のこと。度量衡制度が定められ尺度にこま尺、斗量と検衡に唐制を採用、尺・升・斤とも大小二種とされます。
以降、日本のはかりの発達は、経済と切っても切れない縁で切れない関係となりました。それもそのはずで、物々交換するにも、まずは量をはかることが必要だったからです。
鎌倉・室町時代には両替商の活動が盛んになり、銅銭が全国各地に流通します。砂金や切銀も秤量貨幣として使われ始めます。金や銀を扱う職業柄、かんざし職人や彫金師が天秤を使って「はかる」仕事を請け負うようになり、そうした人たちが後に「目盛り師」と呼ばれるはかりの一流職人に。当然、はかりの精度も飛躍的に向上しました。
江戸時代になると、金銀の量を全国各地で同じようにはかる必要性にせまられました。貨幣として江戸が金を、大阪が銀を扱うようになり、公平な商業を営むために計量の基準をつくらなければならなかったのです。そこで幕府は、はかりの製造を統一。江戸と京都に秤座(はかりざ)をおきます。
秤座とは、秤の製造から販売、補修や検査までを一手に行うところ。
江戸では守随(しゅずい)家(守随彦太郎)が東の33ヵ国を、京都では神(じん)家(神善四郎)が西33ヵ国の秤座となりました。
このようにはかりは幕府の厳しい統制下におかれ、それ以後は秤座で作った以外のはかりはすべて偽ばかりとされ厳しく罰せられました。。「にせ秤つくりしものは、・・・」として重罪が課せられたことからも統制に重きをおいていたことが分かります。はかりを直すのも秤座だけができる仕事ですから、「ちょっと調子が悪いから」といって勝手に修理することはできません。現に、許可なく修理して、罰せられた人も大勢いました。また秤座はおよそ10年に一度、秤をチェックして正常なはかりには焼き印を押して品質を保証し、悪いはかりは廃棄したそうです。
とは言え、京都と江戸(東京)の2軒だけの秤座が日本中のはかりの製造からメンテナンスまですべて行うには無理があります。例えば遠方から大きな竿ばかりの注文がきたとき、重りを鋳造して運ぶだけでも大変です。そこで各地に出張所を置いて、全国の秤のニーズに応えていました。
取材協力:秤乃館
