POSへの対応
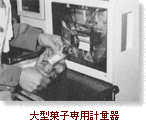
昭和49年、このころのスーパーマーケット業界では、計量機のもっと高度な活用方法を模索していました。なぜなら多店舗展開で業容が拡大するにしたがって戦略決定のための情報収集が複雑かつ、多岐に及んできます。どの商品がどれだけ売れたかというリアルタイムなデータをできるかぎり正確にキャッチし、次の商戦に活用するということなのですが、このやり方にPOS、つまりポイントオブセールス(販売時点管理)という方法があります。
売場のレジスターに正札読み取りなどの機能を持たせ、それを端末として本社などのコンピューターと連動させ、販売時点で即時的にデータが入力され、伝票整理、帳簿計算などの売上管理、在庫管理、商品管理を行っていきます。例えば自動値付機などもレジスターの販売情報のフィードバック、あるいは仕入れやチェーンオペレーション情報処理システムの端末機として有効な機能をもっているのです。これにはコンピューターシステムによる情報処理のオンライン化というテーマが必ずつきまとうわけですが、いずれにせよこうしたPOSシステムをいかに効率よく構築していくかということに尽きます。
POSシステム用ラベルプリンターは、製品を計量、包装すると同時に、可視数字で自動的に値付けを行うとともに、POSターミナルのオートリーダーで読み取り可能なバーコードを出力します。バーコードはレジスターを通して販売時点のナマ情報として本部コンピューターに入力されるPOSシステムのいわば最前線の機能を果たすものです。
今日ごくあたりまえとなったPOSシステムも当時のPOSシステム用ラベルプリンタからはじまりました。
