壁画が教えてくれる
大昔の天秤
紀元前~700年頃
縄文時代~古墳時代
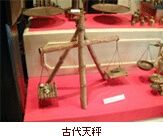

間が最初にはかったものは「時間」であると考えられています。人々が農耕を始めると、種をまくタイミングや洪水が起こりやすい季節、収穫の時期をよむことが必要になったからです。時間の測定には、太陽や星の位置、月の満ち欠けを調べて時間をはかるようになります。マヤ文明の最盛期には、長年にわたる天体観測よって精密な暦(マヤ暦)が生まれています。
やがて道具や掘っ建て小屋をつくるようになると、その「長さ」をはかるようになり、また穀物を交換するために「体積」をはかるようになりました。「重さ」がはかられるようになるのは、それからずっと後のことです。都市国家が整えられていくにつれて、貴金属や宝石が大切にされるようになり、その価値をはかろうとしたのです。
重さをはかるために、人間が最初につくり出した機構をもつ計器が天秤です。人が腕を水平に上げたときの形をしている天秤。1本の棒の中心を支点に、水平の棒の両端に皿をつるして、片方に「分銅」と呼ばれる重りをのせてバランスをとり、モノの重さをはかります。現代の人々から見れば、単純なつくりのはかりですが、天秤の発明ははかりの歴史の大きな一歩でした。いつ誕生したのかは定かではありませんが、エジプトで紀元前5000年ごろのものと思われる天秤が見つかっています。また古代エジプトの壁画には、鍛冶工場で天秤を使って作業をしている様子が描かれたものがいくつかあります。
天秤は数千年にわたって、人の暮らしの中で唯一のはかりとして利用されます。ローマ時代になって、棹ばかりが登場。1本の棹と一つの重りで、一定の範囲の重さまでをはかれるようになりました。
古代は人々がはかることに大きな夢をかけた時代だったのかもしれません。ちなみに紀元前250年頃にはギリシャの博物学者、エラトステネスがエジプトで地球の大きさをはかろうとしました。
すでに地球が球体であると考えていたのです。古代の人々の賢明さと「はかる」ことにかける情熱の大きさには驚かされるばかりです。
取材協力:秤乃館
